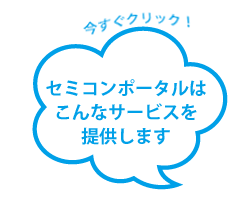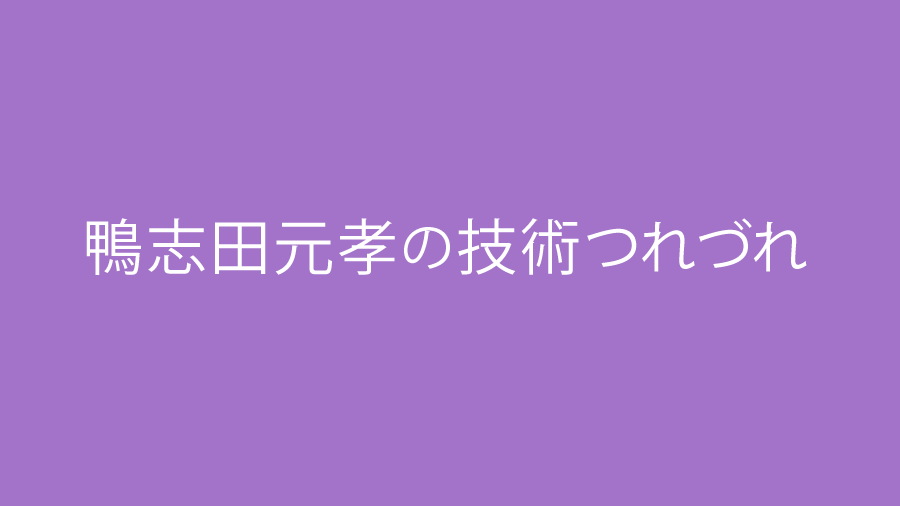
2025年7月23日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
ĖĮ┬Õż╬AIĄĪ▀_(d©ó)ż¼žQż©żļŠ├õJ┼┼╬üż╬▓▌¼ö▓“»éż╦Ė■ż▒żŲźżź╬ź┘Ī╝źĘźńź¾Č\Įčż“├Ążļų`┼¬żŪĪóź╗ź▀ź│ź¾╩¼╠Ņż╦µu└▄ż╣żļ╩¼╠Ņż╬ŃKų`╚¼ų`ż“╣įż├żŲżŁż┐ĪŻźąźżź¬╩¼╠ŅżŽź╦źÕĪ╝źĒź¾ż╬╗┼┴╚ż▀ż╩ż╔Š╩┼┼╬üźĘź╣źŲźÓż“├Ążļų`┼¬żŪĖ½żŲż¬ż½ż═żąż╩żķż╩żżĪŻØi╩¾2įćĪ╩Īų░Õ╣®ŽóĘ╚ż╬┐╩▓Įż“╦ŠżÓĪ╩żĮż╬1Ī╦ż¬żĶżėĪ╩żĮż╬2Ī╦ĪūĪ╦ż╦ż¬ż▒żļźąźżź¬ż╬├µżŪżŌØŖż╦AIż╦ŖZżżż╚╗ūż’żņżļ░Õ╣®ŽóĘ╚ż“Ū┴żŁżĮż╬▓▌¼öż╚×┤║÷ż“ĄŁĮężĘż┐ĪŻDNAż╬ĄōĀaĪóöv╔³ż╬źßź½ź╦ź║źÓż╦┤žż╣żļ└Ō£½▐kż─ż“Ė½żŲżŌ░Õż╬╝┬ézż╬ŠņżŪżóżļĻā▒Īż╬└Ō£½żŽ▐k╚╠┤ĄŪvż╦ż╚ż├żŲžM▓“żŪżóżļĪŻ▐köĄ(sh©┤)╣®│žż╬╝┬ézż╬ŠņżŪżóżļ╣®ŠņżŪżŽ║ŅČ╚ź▀ź╣ż“╦╔ż░ż┐żßĪóźŪĪ╝ź┐ż╬Īų▓─£å▓ĮĪūż“┤ż╦ż’ż½żĻżõż╣żĄż“ŗī▐kż╦żĘż┐║ŅČ╚╗žŲ│ż“╣įż”┤╔═²Č\ĮčżŌ╗╚ż’żņżŲżżżļĪŻ╣®│žżŪżŽ┤╔═²Č\Įčż╚═ū┴ŪČ\Įčż╚ż¼┘Zż╬╬ŠåĶż╩ż╬żŪĪó░Õ│žżŌżĮż╬╬ŠåĶż“╣ńż’ż╗żŲŲDżĻ╣■ż▀Īó░Õ╣®ŽóĘ╚ż“┐▐żļØŁ═ū└Łż“└Ōżżż┐ĪŻ└┌żĻĖ²ż¼┼¬│░żņż└ż├ż┐ż╬ż½żŌżĘżņż╩żżż¼Īó░Õ╣®ŽóĘ╚ż½żķżŽAIż╬Š╩┼┼╬üźżź╬ź┘Ī╝źĘźńź¾ż╦┤žż╣żļ═Į├¹żŽĖ½żżż└ż╗ż╩ż½ż├ż┐ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
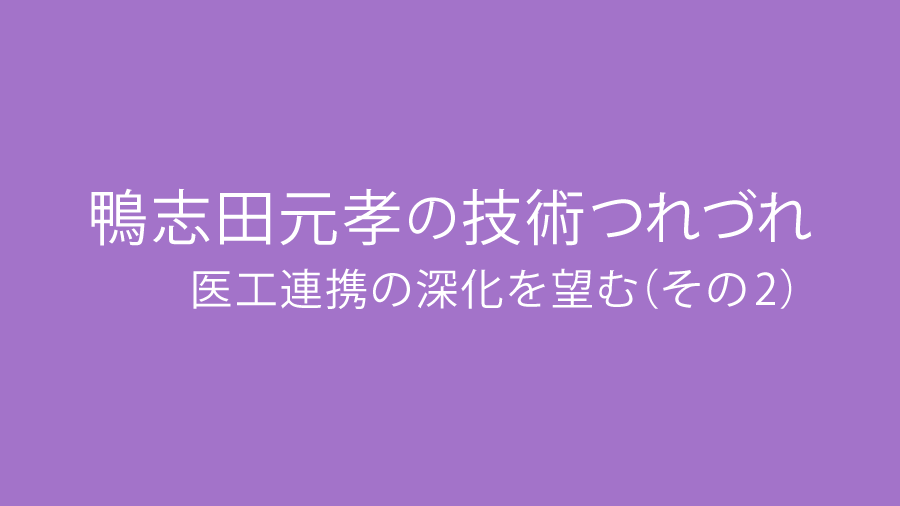
2025年7月 9日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
Øi╩¾Ī╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦żŪ░Õ╣®ŽóĘ╚ż╦ż─żŁĪó░Õ│žż╬╬ūņoĖĮŠņżŪ╗╚ż’żņżŲżżżļ┤ĄŪvż╦×┤ż╣żļ└Ō£½Į±ż╬žM▓“żĄż“ĄŁĮężĘż┐ĪŻ╦▄ąMżŪżŽAIż╬Įø(j©®ng)═Ķ│ū┐ĘČ\Įčż“├Ążļų`┼¬żŪŃKų`╚¼ų`ż“żĘżŲżżżļż╬żŪĪóżóż▐żĻ┐╝Ų■żĻżŽż╗ż║Īóż┐ż└╝┬▌åż“ē¶żļż┐żßż╬ĖĮėXŪ¦╝▒µć┼┘ż╦╣═ż©żŲż¬Ų╔ż▀żżż┐ż└żŁż┐żżĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
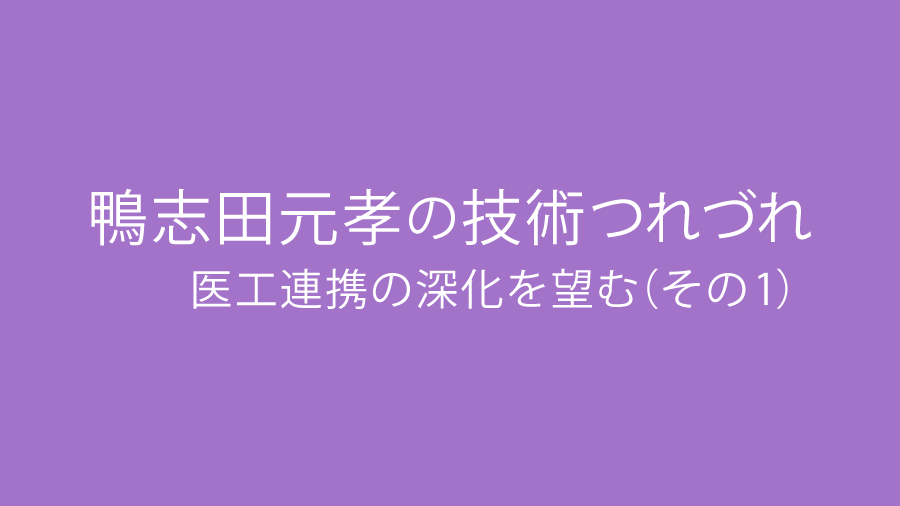
2025年7月 9日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
ĖĮ┬Õż╬AIĄĪ▀_(d©ó)ż╦żŽŠ├õJ┼┼╬üż╬▓▌¼öż¼żóżļż╬żŪźżź╬ź┘Ī╝źĘźńź¾ż¼ØŁ═ūż╩ż│ż╚żŽ├»żĘżŌ╗ūż”ż│ż╚żŪżóżļż¼Īó▓┐ż“ż╔ż”ż╣żņżążĶżżż╬ż½żŽÅSų`Ė½┼÷żŌż─ż½ż╩żżĪŻż│ż”żżż”╗■żŽ┐╚ŖZż╩ŠÅČ╚╩¼╠Ņż“╗■Ī╣─»żßżŲż▀żļż│ż╚żŌØŁ═ūżŪżóżļĪŻżżż’żµżļŃKų`╚¼ų`żŪżóżļĪŻ╦▄ąM░╩æTżĘżążķż»źąźżź¬ż╚Ė„│ž╩¼╠Ņż╬ĖĮėXż“Ū┴żżżŲż▀ż┐żżĪŻĖ„│žżŪżŽŠ╩¾┼┴┴„ż╬Š╩┼┼╬üż╚żżż”┴T╠ŻżŪźšź®ź╚ź╦ź»ź╣żõ╬╠╗ęŠÅČ╚ż¼ź╗ź▀ź│ź¾ŠÅČ╚ż╚µu└▄żĘżŲżżżļĪŻż▐ż┐źąźżź¬żŽź╦źÕĪ╝źĒź¾ż╬╗┼┴╚ż▀ż╩ż╔Š╩╬üźĘź╣źŲźÓ┤žĘĖżŪĖ½żŲż¬ż½ż═żąż╩żķż╩żżĪŻż╚żŽżżż├żŲżŌĪó╬ŠŪvż╚żŌżóż▐żĻż╦╣Łżżż╬żŪż╔ż│ż“Ū┴ż»ż½ĪóżĮż╬└┌żĻĖ²ż¼─_═ūż╦ż╩żļĪŻ╔«Ūvż╬Ų╚éāż╚╩ąĖ½żŪ░Õ┬ä┤žĘĖĪóØŖż╦░Õ╣®ŽóĘ╚ż½żķŲ■żļż¼ĪóżĮżņżŽ╔«Ūvż╬Ė─┐═┼¬ż╩Ą£ŠżŌżóżļż╬żŪĪóżĮżņż╦żĶżļ╩ążĻżŽżóżķż½żĖżßż┤╬╗ńR─║żŁż┐żżĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
![ź┘ź¾ź┴źŃĪ╝┤ļČ╚ż¼ŠW(w©Żng)▒ūż“Ö┌żÓż▐żŪż╬┤³┤ųø]Į╠ܦ▐qż╬ż┐żßż╬Įo╬®ż╬źūźķź├ź╚źšź®Ī╝źÓ└▀╬®ż“─¾░Ų ź┘ź¾ź┴źŃĪ╝┤ļČ╚ż¼ŠW(w©Żng)▒ūż“Ö┌żÓż▐żŪż╬┤³┤ųø]Į╠ܦ▐qż╬ż┐żßż╬Įo╬®ż╬źūźķź├ź╚źšź®Ī╝źÓ└▀╬®ż“─¾░Ų](/assets_c/900px/250307-startupsupport.png)
2025年3月 7日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
ŗī46övITE╣±║▌▓Ķ楥Ī▀_(d©ó)·t2024Ī╩źčźĘźšźŻź│▓Ż┘pĪĪ12ĘŅ4-6Ų³Ī╦ż╦ĄūżĘżųżĻżŪ╝┬║▌ż╦Ė½│žż“żĘżŲżŁż┐ĪŻ╔«Ūvż╬░§ō■(j©┤)żŽĪó1)ų`┼¬ż╦╣ńż’ż╗ż┐šJ(r©©n)░ŽżŪ╗@┼┘ż“Ė■æųżĄż╗ż┐AIż╬╝┬äó▓Įż¼┐╩ż¾ż└ż│ż╚ż╚Īó2)źšź®ź╚ź¾ż╬╚¶╣į╗■┤ų▒R─ĻČ\ĮčĪ╩Time of FlightĪ©░╩▓╝ToFż╚ŠSĄŁĪ╦ż╬│½╚»╝┬├ō▓Įż¼┐╩·tżĘżŲżŁż┐ż│ż╚żŪżóż├ż┐ĪŻ┘Jż╦╚»╔ĮżĄżņżŲżżżļ╦▄ĄĪ▀_(d©ó)·tż╬ź┘ź╣ź╚Įą·t╝ęźóź’Ī╝ź╔ż╦ź└źżź╚źĒź¾╝ęż¼┬ō(li©ón)żążņżŲż¬żĻĪ╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦ĪóŲ▒╝ęż╦┐┤żĶżĻĖµĮ╦╗ņż“┐ĮżĘæųż▓ż┐żżĪŻż│żņżŽżĮż╬┬ō(li©ón)─Ļ┤ØŹżŪżóżļĪų└Ō£½µ^ż╬ē¶╝▒Ī”Š╩¾Ī”─¾░Ų╬üĪūżžż╬äh▓┴┼∙ż╬ćĶ┼└żŪ┬ō(li©ón)żążņżŲżżżļĪŻżĘż½żĘ╦▄ąMżŽżĮż”żŪżŽż╩ż»ĪóČÉż»ż▐żŪżŌ╔«Ūvż╬Ė─┐═┼¬ż╩Č\Įč┼¬Ė½▓“żŪżóżļż│ż╚ż“═Įżßż¬éāżĻżĘżŲż¬ż»ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
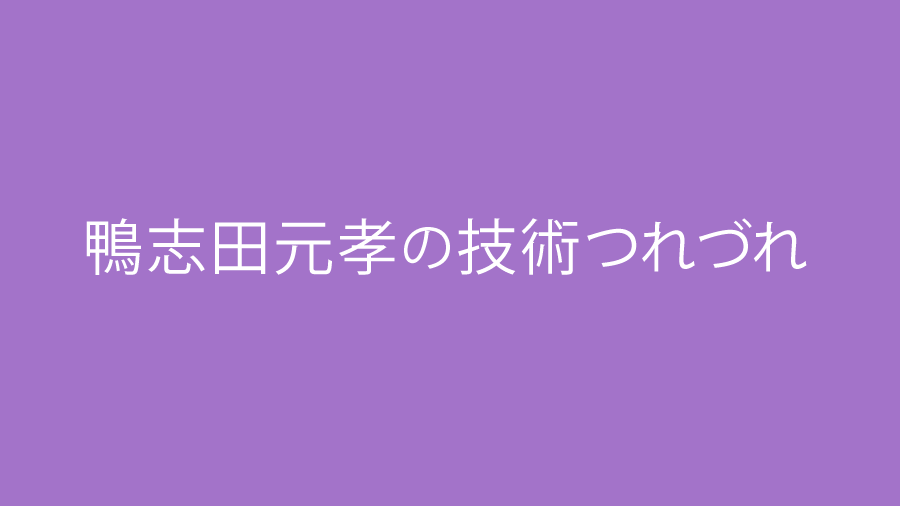
2024年10月 4日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
ØiįćĪ╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦żŪźūźķź¾ź╚└▀╝ŖĪóØŖż╦╣®ŠņĘ·▓░└▀╝Ŗ╗■ż╬ÅR┴TĄ£╣Óż╬▐k╬Ńż“ż▐ż╚żßżŲĄŁĮężĘż┐ĪŻÉ║öü┼¬ż╦żŽĪóĪų„[─Ļ│░Īūż└ż├ż┐▓Į│ž╠¶ēäśOŲ░Ū█┴„ź┐ź¾ź»ż╬Ū█┤╔ż¼│░żņż┐Ą£Ė╬Ą£╬Ńż“¼ö║Óż╦żĘżŲĪóÖ┌└«AIżõ▓Š„[ȧ┤ųČ\Įčż“Ņ~╗╚żĘżŲĪóżĮż╬Ą£Ė╬ż“Īų„[─ĻŲŌĪūż╦żĘĪó×┤║÷ż“ņo╣Įļ]└▀╝Ŗ╗■ż╦“EżĻ╣■żÓ┤─ČŁĪ”ŖWµ£ČĄ░ķ├ōČĄ║Óż“─¾░ŲżĘż┐ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
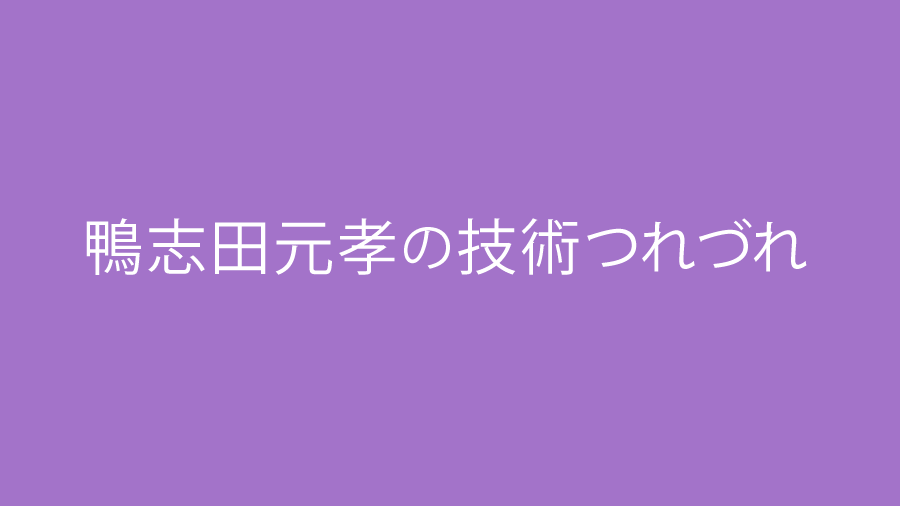
2024年10月 2日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
Øi╩¾Ī╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦żŪ╚ŠŲ│öü×æļ]┐═║Ó░ķ└«ż╦┤žżĘżŲČĄ░ķź½źĻźŁźÕźķźÓ╬®░Ų║Ņ└«ż╬─_═ū└Łż“└ŌżŁĪóżĮż╬▐k╬Ńż“┐āżĘż┐ĪŻżĮż╬┬Šż╦żŌ─_═ūż╩ČĄ░ķ╩¼╠Ņż╬▐kż─ż╦┤─ČŁĪ”ŖWµ£ČĄ░ķż¼żóżļĪŻ┤─ČŁ╩▌µ£ż╚║ŅČ╚ŪvŖWµ£ż╚żŽ╩╠ż╬ź½źŲź┤źĻĪ╝ż╚żŌ╣═ż©żķżņżļż¼Īó┴ĻĖ▀ż╦┤žŽóż╣żļĄ£╣ÓżŌ¾Hżżż╬żŪĪó╦▄ąMżŪżŽż▐ż╚żßżŲĄŁĮęż╣żļĪŻ╦▄ąMż╬ų`┼¬żŽ╚ŠŲ│öü×æļ]Č\Įč┤žĘĖŪvż╦┤─ČŁĪ”ŖWµ£ČĄ░ķż╬źŲĪ╝ź▐żóżļżżżŽ¼ö║Ó╬Ńż“ż¬┐āżĘżĘĪó£p╣ųÖ┌ż¼śO╩¼ż╬Ą£ż╚żĘżŲ┬¬ż©żŲżŌżķż©żļżĶż”ż╩╝┬éz┼¬ż╩źŲźŁź╣ź╚żõź╣źķźżź╔ĪóźėźŪź¬ż╩ż╔ż╬ČĄ║Óż“║Ņ└«żĘżŲ─║ż»ż┐żßż╬┴Ū║Óż“ČĄ░ķŪvż╦─¾ČĪżĘżŲĪó┤─ČŁĪ”ŖWµ£ČĄ░ķż╬▐kÕ\ż╚żĘżŲ─║ż»ż│ż╚ż╦żóżļĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
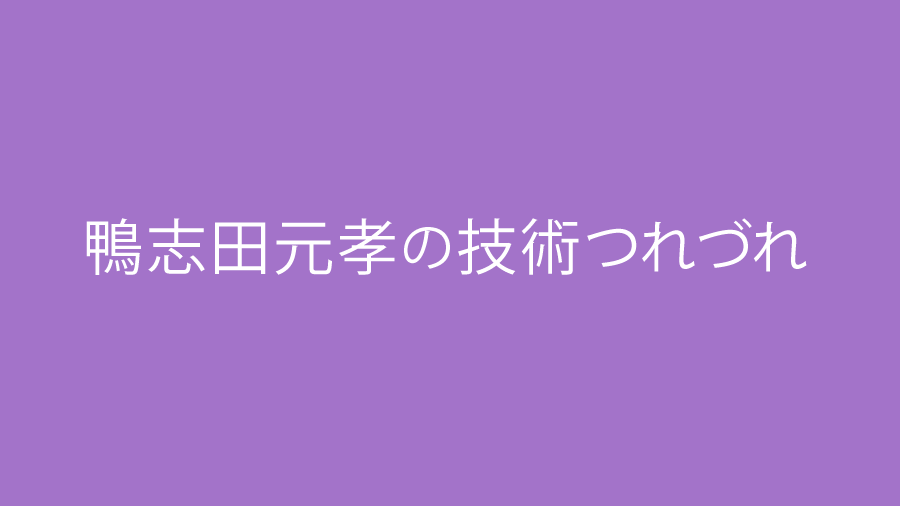
2024年6月 6日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
┐═║Ó░ķ└«ČĄ░ķźūźĒź░źķźÓżŪżŽź½źĻźŁźÕźķźÓż╬╣Į└«ż¼Ė░ż╚ż╩żļĪŻż▐żĘżŲ░┼╠█ē¶ż¼¾Hżż×æļ]╩¼╠ŅżŪż╬ČĄ░ķźūźĒź░źķźÓż╚ż╩żļż╚Īó╝å╩╣żŽ▐kĖ½ż╦ŪĪż½ż║żŪĪó╝┬éz┼¬ż╩żŌż╬ż¼ØŁ═ūżŪżóżļĪŻ╩ĖŠŽżŪĮ±ż½żņżŲżżżļźŲźŁź╣ź╚ż└ż▒żŪżŽŠ╩¾╬╠ż¼ż╔ż”żĘżŲżŌĖ┬żķżņżŲżĘż▐ż”ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
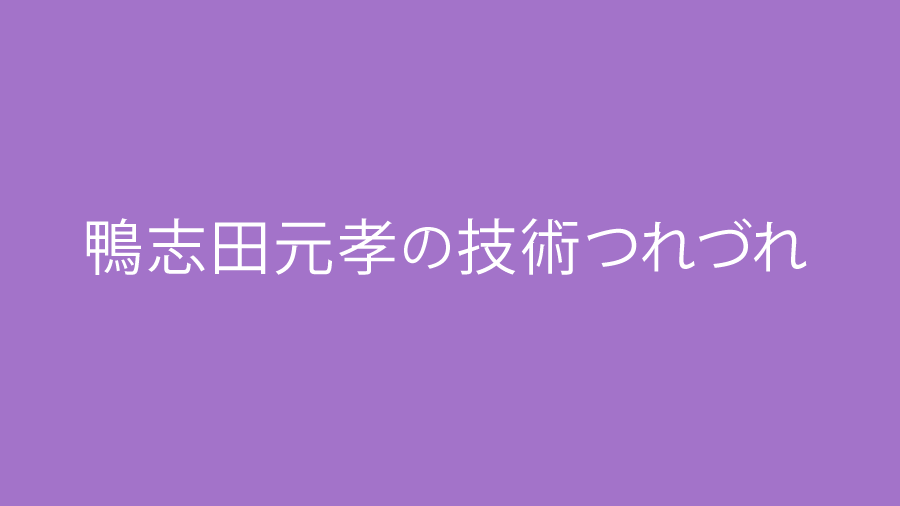
2024年4月16日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
Ų³╦▄ż╬╚ŠŲ│öü╔³īÖż╬ż┐żßż╦żŽ┐═║Ó░ķ└«ż¼’L(f©źng)ż½ż╗ż╩żżĪŻż│żņż▐żŪä▌╣±ż╬Ž×║÷ż╩ż╔ż“Šę▓żĘżŲżŁż┐Ī╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦ż¼Īó║Żż╦ż╩ż├żŲżŌĪó├»ż¼Īóż╔ż│żŪĪóżżż─ż▐żŪż╦Īó▓┐ż“żõż├żŲĪó┐═║Ó░ķ└«ż“╝┬╣įż╣żļż╬ż½ĪóĄšż╦żĮż╬╝Ŗ▓Ķż╩żĻ└’ŠSż“╝┬╣įż╣żņżą╦▄┼÷ż╦┐═║Ó░ķ└«ż¼żŪżŁżļż╬ż½ż╚żżż”ż╚ż│żĒż▐żŪ╝čĄ═żßż┐É║öü║÷ż¼Īóź═ź├ź╚ż“├ĄżĘżŲżŌĪ󿎿├żŁżĻĖ½ż©żŲż│ż╩żżż╬żŽĪóż▐ż└╔«Ūvż╬ĖĪ║„ē”╬üż¼╔į’BżĘżŲżżżļż½żķż└żĒż”ż½ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
![×æļ]Č╚ż¼Ö┌└«AIż“Ų│Ų■ż╣żļ║▌ż╬é╬┴T┼└ĪĮ×óż©żóżņżą═½żżż╩żĘ ×æļ]Č╚ż¼Ö┌└«AIż“Ų│Ų■ż╣żļ║▌ż╬é╬┴T┼└ĪĮ×óż©żóżņżą═½żżż╩żĘ](/assets_c/900px/230613-manufacturinggenai.png)
2023年6月13日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
OpenAI╝ęż╬ChatGPTż╦┬Õ╔ĮżĄżņżļÖ┌└«AIżŽĪóMicrosoftżõGoogleż╬╗▓Ų■żŪĪóż▐ż╣ż▐ż╣│½╚»ż╬└¬żżż“╗\żĘżŲżżżļĪŻ║ŪŖZżŌOpenAIĪóOpenResearchĪóUniversity of Pennsylvaniaż¼Č”├°żŪĪųGenerative Pre-trained Transformers (GPTs)żŽgeneral-purpose technologies (GPTs)żŪżóżļĪūĪóż─ż▐żĻGPTżŽ└@├ōČ\ĮčżŪżóżĻĪó╣Ō─┬ČŌż╬╗┼Ą£ż╬Ė·╬©ż“╣Ōżßżķżņżļż╚╩¼└ŽżĘżŲżżżļĪ╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦ĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]

2023年3月14日
Ī├ļr╗ų┼─ĖĄ╣¦ż╬Č\Įčż─żņż┼żņ
ITMedia Virtual EXPO 2023 Įšż¼2023ŃQ2ĘŅ14Ų³-3ĘŅ17Ų³ż╦│½╠¢żĄżņż┐Ī╩╗▓╣═½@╬┴1Ī╦ĪŻĘ·└▀Č╚ż╚×æļ]Č╚ż╬źŪźĖź┐źļ┴Ē╣ń·tż╚żĘżŲĪóżĮż╬ć@ż╬─╠żĻźąĪ╝ź┴źŃźļ·t┐ā▓±żŪżóżļĪŻż│ż╬¹|ż╬·t┐ā▓±żŽĪó½@╬┴żõŲ░▓Ķż¼źóĪ╝ź½źżźųż╦ż╩ż├żŲżżżŲĪóĄ’ż╩ż¼żķż╦żĘżŲĪóżżż─żŪżŌ£å─░żŪżŁżļż╬żŪØÖŠ’ż╦żóżĻż¼ż┐żżĪŻ╦▄ąMżŪżŽĘQźųĪ╝ź╣ż“╦¼╠õżĘĪóAI&IoTż╦┤žż╣żļŠ╩¾ż“╝²ĮĖżĘżŲĪóč©▒█ż╩ż¼żķ╔«Ūvż╩żĻż╦żĮż╬Ų░Ė■ż“╩¼└ŽżĘż┐±T▓╠ż“ż▐ż╚żßżļĪŻ
[ó¬¶öżŁż“Ų╔żÓ]
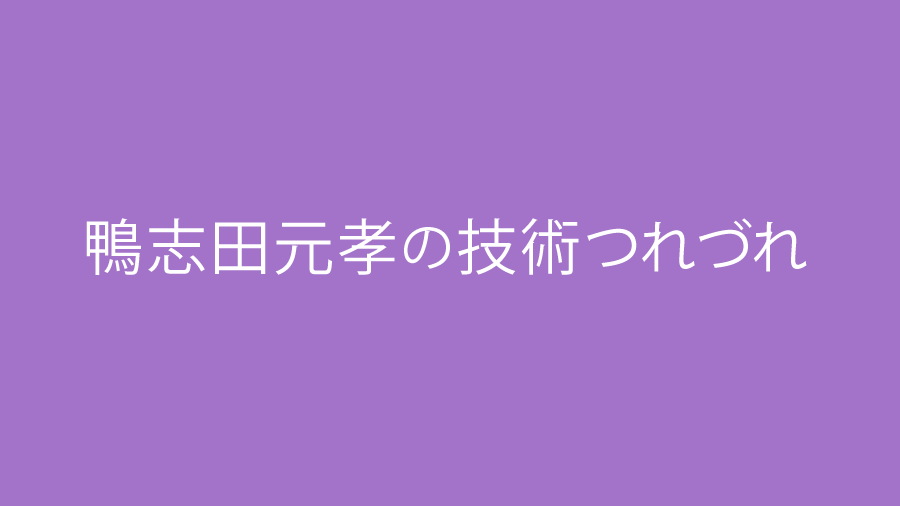

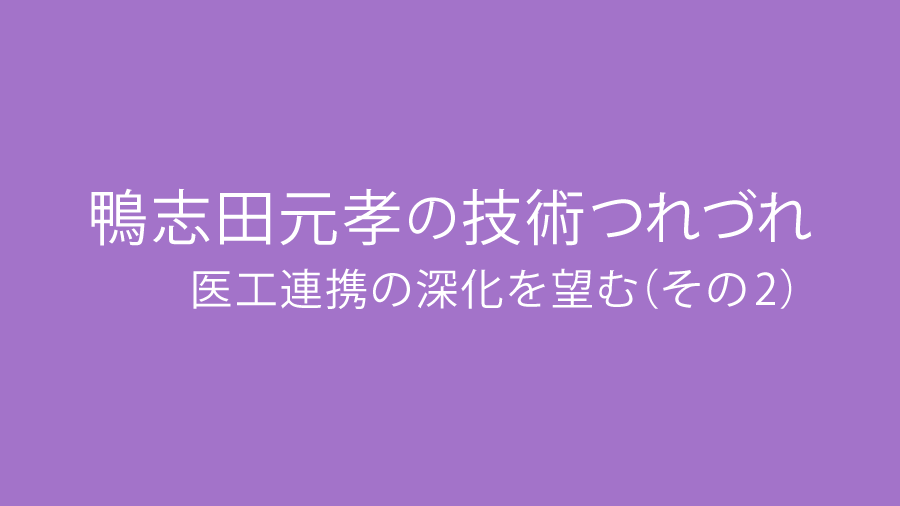
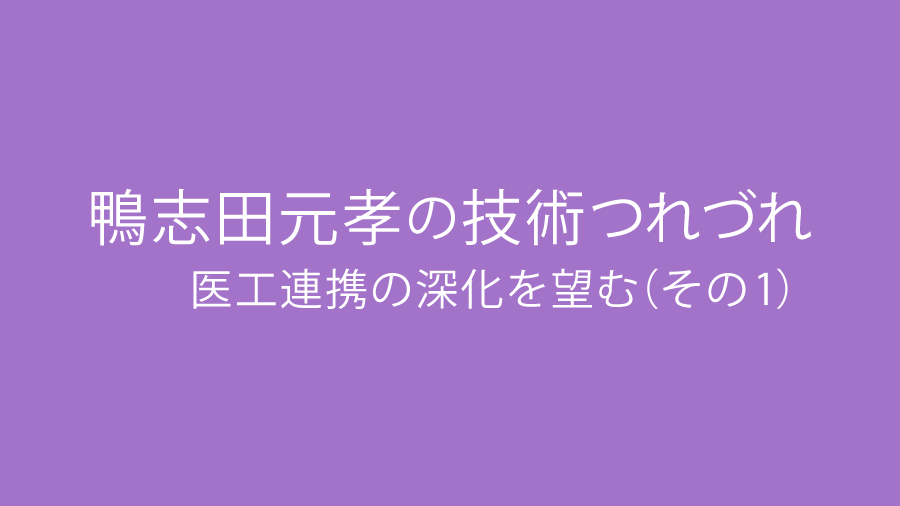
![ź┘ź¾ź┴źŃĪ╝┤ļČ╚ż¼ŠW(w©Żng)▒ūż“Ö┌żÓż▐żŪż╬┤³┤ųø]Į╠ܦ▐qż╬ż┐żßż╬Įo╬®ż╬źūźķź├ź╚źšź®Ī╝źÓ└▀╬®ż“─¾░Ų ź┘ź¾ź┴źŃĪ╝┤ļČ╚ż¼ŠW(w©Żng)▒ūż“Ö┌żÓż▐żŪż╬┤³┤ųø]Į╠ܦ▐qż╬ż┐żßż╬Įo╬®ż╬źūźķź├ź╚źšź®Ī╝źÓ└▀╬®ż“─¾░Ų](/assets_c/900px/250307-startupsupport.png)
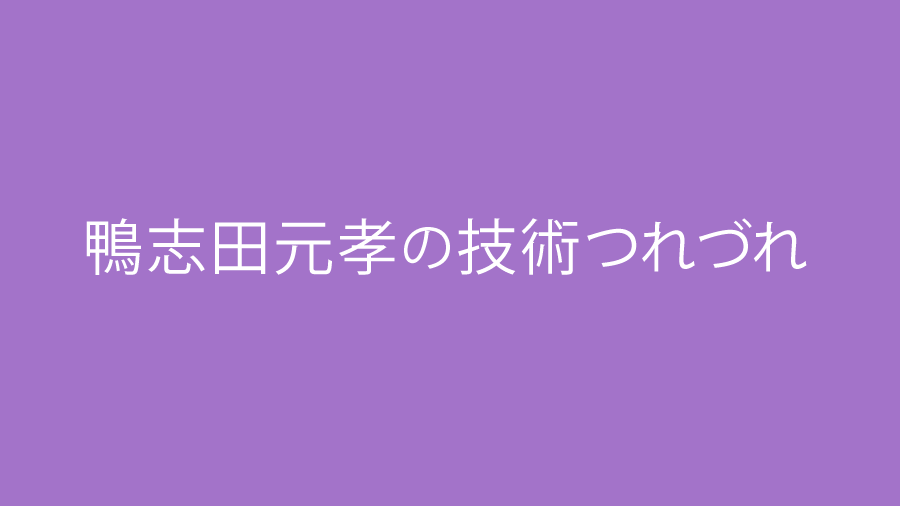
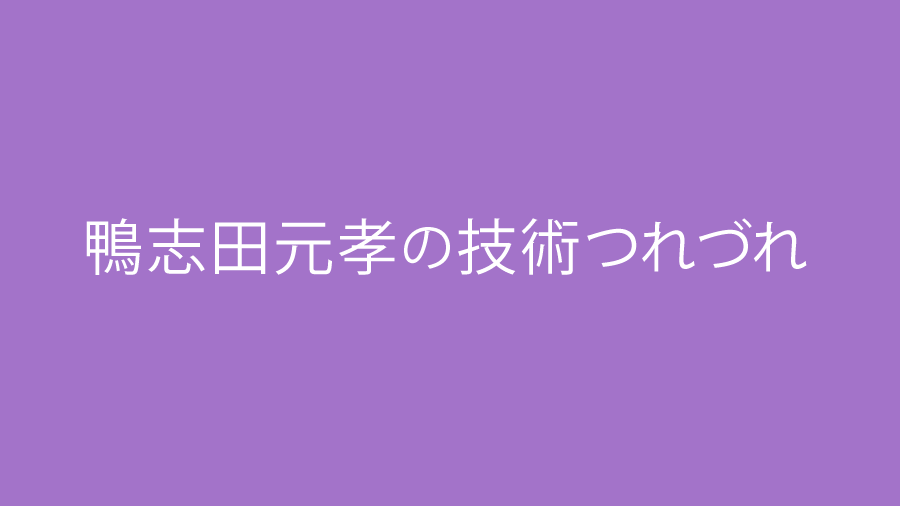
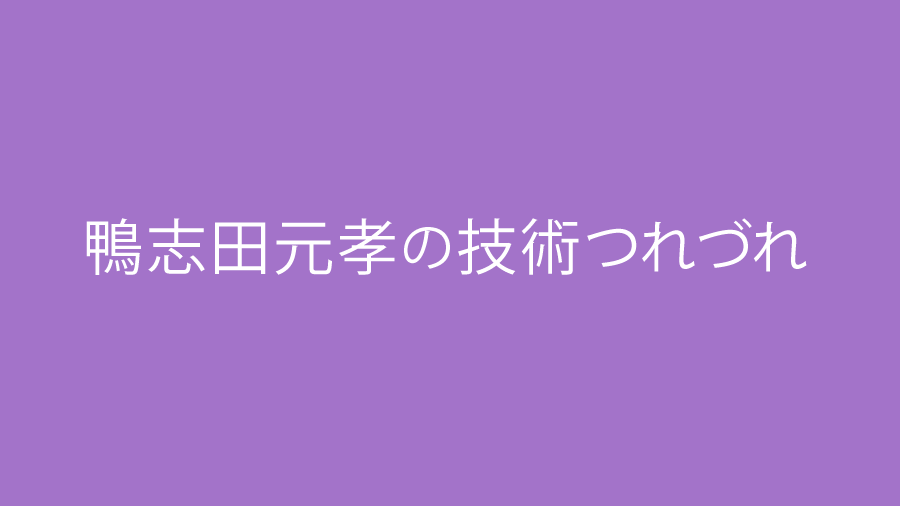
![×æļ]Č╚ż¼Ö┌└«AIż“Ų│Ų■ż╣żļ║▌ż╬é╬┴T┼└ĪĮ×óż©żóżņżą═½żżż╩żĘ ×æļ]Č╚ż¼Ö┌└«AIż“Ų│Ų■ż╣żļ║▌ż╬é╬┴T┼└ĪĮ×óż©żóżņżą═½żżż╩żĘ](/assets_c/900px/230613-manufacturinggenai.png)