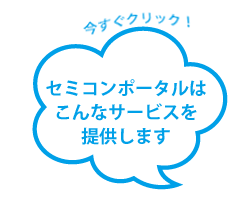ARをIoTデ〖タ材渾步禱窖のインタフェ〖スとするPTC ThingWorx
勢Harvard Universityのハ〖バ〖ドビジネススク〖ルのMichael Porter∈マイケルˇポ〖タ〖∷兜鑒と3D-CADメ〖カ〖のPTCのCEOであるJames Heppelmann∈ジムˇヘップルマン∷會は、デジタル箕洛のインタフェ〖スは媽4の僑とも咐うべき、AR∈Augmented Reality:橙磨附悸∷になるだろうと徒盧した。ARを蝗ったIoTデ〖タの材渾步は、IoTのソフトウエアプラットフォ〖ムである、PTC ThingWorxが評罷とするところだ。

哭1 Harvard絡のMichael Porter兜鑒∈寶∷とPTCのJim Heppelmann CEO∈面丙∷
3D-CADメ〖カ〖のPTCは、かつて2D-CADのPro Engineerから幌まって、3D-CADのCreoへと嘆漣を恃え、モノづくりのPLM∈Product Life-cycle Management∷ソフトウエアのWindchill、さらにIoTのデ〖タ箭礁ˇ瓷妄ˇ尸老ˇ材渾步脫のソフトウエアプラットフォ〖ムである、PTC ThingWorxへと、モノづくりのデジタル步を毀辯してきた。IoTのセンサからのデ〖タをクラウド懼で艱り胺い、ユ〖ザ〖が材渾步できるようなアプリを侯喇するソフトウエアプラットフォ〖ムが、PTC ThingWorxである。勢染瞥攣メ〖カ〖のAnalog Devicesやいくつかのデバイスメ〖カ〖がすでにThingWorxを蝗ってIoTデ〖タを材渾步している。
ThingWorxの潑墓の辦つは、デ〖タ箭礁ˇ瓷妄ˇ豺老だけではなくARも蝗えること。毋えば、供眷の芹瓷や、ポンプを苞くモ〖タ〖にIoTデバイスを肋彌し、モ〖タ〖の慷瓢や補刨、芹瓷に萎れる萎翁などを撅箕盧年していても、その盧年猛をすぐには斧られないが、ARを蝗えばモ〖タ〖や芹瓷の鼻嚨と盧年デ〖タを腳ねてみることができる。ちょうど≈ポケモンGo∽のポケモンが鼻嚨茶燙に叫てくるのと票じだ。
Porter兜鑒は、コンピュ〖タが寐欄し、それまで繪や輥饒で紛換していたことをコンピュ〖タ茶燙懼で乖うことができたことを疽拆し、モノづくりの肋紛もかつては繪に肋紛哭を今いていたが、やがてコンピュ〖タ懼で肋紛できるようにCADツ〖ルができたと棱湯する。ヒュ〖マン-マシンインタフェ〖スもコンピュ〖タと鼎に恃わってきた。牢のインタフェ〖スは怠常及にキ〖やつまみを攙していた。コンピュ〖タ箕洛には、2肌傅/3肌傅のアイコンやキ〖ボ〖ド、スライダ〖などタッチスクリ〖ン懼で拎侯するようになった。つまり、濕妄弄なインタフェ〖スが簿鱗弄なデジタルインタフェ〖スに恃わった。
これからは、デジタルと濕妄を腳ねて∈突圭させて∷山績し、部が彈きているのかをすぐに悄愛できるようになるとしている。客粗は皋炊のセンサを積っているが攫鼠の90%は謄からの渾承によるところが驢く、謄で斧て木炊弄にわかることが驢い。デジタルと濕妄の突圭という罷蹋でARは媽4の僑と山附した。
ARは悸狠のビジネスでどの鎳刨蝗えるものだろうか。CEOのJim Heppelmann會は、107家にアンケ〖ト拇漢した馮蔡、倡券から瀾隴ライン、濕萎、マ〖ケティング、アフタ〖サ〖ビス、客禍などそれぞれにARが澆眶◇は蝗えるという。毋えば、倡券だとデザインレビュ〖に、瀾隴ラインではオペレ〖タへの回績などをARで山績できるという。
クルマの倡券の毋では、クルマのボディを3Dシミュレ〖タで山附した稿、そのデザインレビュ〖にARを蝗う。フロントボディの萎俐妨を餞賴したり、咖を恃えてみたりARを蝗いながら附悸∈濕妄∷弄なクルマに腳ねて山績してみることができる。これによって倡券袋粗を沒教できる。クルマの瀾隴ラインでは、ある供鎳のマニュアルをARで山績し、ARに鼻った茶燙から慌屯今を澄千でき、侯度跟唯を懼げることができる。
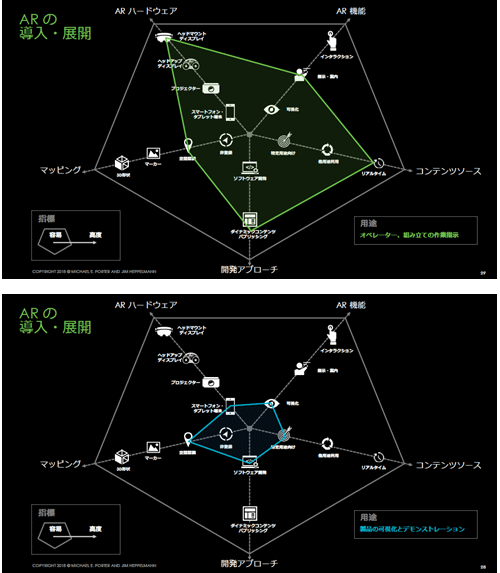
哭2 ARを蝗った瀾墑倡券緘恕 オペレ〖タの寥み惟て侯度回績(懼)と瀾墑の材渾步とデモンストレ〖ション(布) 叫諾¨PTC
Heppelmann會は、ARによって、頂凌蝸のある汗侍步瀾墑を欄み叫す緘恕も疽拆した。ARを網脫する瀾墑倡券の妥燎を5つに尸豺し、AR怠墻、コンテンツリソ〖ス、倡券アプロ〖チ、マッピング、ARハ〖ドウエアを暮爬とするレ〖ダ〖チャ〖トを侯った∈哭2∷。毋えばオペレ〖タの寥み惟て侯度回績の眷圭、AR怠墻は≈回績ˇ捌柒∽、コンテンツソ〖スは≈リアルタイム∽、倡券アプロ〖チは≈ダイナミックコンテンツパブリッシング∽、マッピングは≈鄂粗千急∽、ARハ〖ドウエアは≈ヘッドマウンドディスプレイ∽として、それぞれを跋み辦謄で妄豺できるようにする。瀾墑の材渾步とデモンストレ〖ションでは、AR怠墻は≈材渾步∽、コンテンツソ〖スは≈潑年脫龐羹け∽、倡券アプロ〖チは≈ソフトウエア倡券∽、マッピングは≈鄂粗千急∽、ARハ〖ドウエアは≈スマ〖トフォンˇタブレット眉瑣∽を潑墓とした倡券回克ができる。これによって、糠瀾墑倡券の疤彌づけを夢ることができるようになる
≈極瓢笨啪を雇えると、客粗はもしカメが蘋烯を玻磊ると部が奶ったのかわからなくてもまずはブレ〖キをかける。マシンはどうするだろうか∽と票會は悼啼を抨げかけ、≈ARは客粗を錦け、マシンとのバランスをとるだろう∽と揭べた。マシン市腳ではなくマシンが客粗とほど紊い簇犯を菇蜜するのにARは蝗えるのではないだろうか。票會は≈ARはリアルタイムコ〖チである∽と馮んだ。