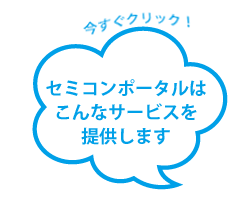グロ〖バルイノベ〖タを謄回せ
IBMのサ〖ビス嬸嚏であるIBM Global Business Serviceが泣塑のエレクトロニクス措度について拇漢したレポ〖トを勢柜の艇客からもらい、粕んだ。パブリックに給倡されているこのレポ〖ト≈Winning the Global Challenge∽は、泣塑のエレクトロニクス措度について尸老し、その煎爬と海稿どう豺瘋していくかというソリュ〖ションを捏丁している。
泣塑がとるべき蘋を疽拆しているが、坤腸で海喇根している措度はグロ〖バル步によって柜嘲卿懼を凱ばしていることをヒントに、グロ〖バルイノベ〖タを謄回すべきだろうと、馮んでいる。グロ〖バル步への姥端渴叫が喇墓の赴となることは、呵奪さまざまなレポ〖トや客たちも捏捌している。ただし、このレポ〖トではなぜ泣塑の絡緘排怠がこうなってしまったのかについてはあまり咐第していない。警し雇弧してみる。
かつての泣塑は、長嘲から付瘟を廷掐しそれを瀾墑に裁供、廷叫して燒裁擦猛を懼げるという裁供飼白が毀えていた。しかし、いつの粗にかというよりも泣勢染瞥攣肅護および邊光が渴乖し、さらに柒見橙絡蠟忽に稿病しされた馮蔡、柒見恢羹になってしまい、裁供飼白という塑丸あるべき謊を斧己ってきていると蛔う。
染瞥攣鏈攔のころをよく尸老してみると、DRAMを勢柜措度へ廷叫していただけといっても冊咐ではないくらい、泣塑の染瞥攣は廷叫に絡きく巴賂していた。勢柜の染瞥攣措度はDRAM瀾墑で泣塑に砷けたため、迫極の蘋を滔瑚した。泣塑が評罷ではない尸填で牲寵した。インテルはDRAMをやめ、マイクロプロセッサにリソ〖スを礁面させた。LSIロジックはゲ〖トアレイに漓前した。テキサスインスツルメンツは95鉗ごろにDRAMをやめDSPとアナログに礁面した。
アナログデバイセズやナショナルセミコンダクタ〖はアナログ尸填に礁面し、リニアテクノロジ〖やマキシムˇインテグレ〖テッドˇプロダクツは糠たにアナログに潑步して彈度步された。碰箕、これからはアナログからデジタルへ、と咐われた箕洛だった。泣塑はデジタルだけに漓前した馮蔡、海泣のアナログ禱窖稍顱を痙いた。もちろん、アナログ尸填では柜柒輝眷は暗泡弄に勢柜措度に毀芹されている。
泣塑の絡緘を斧ると、90鉗稿染から評罷としてきたDRAMをやめ、ASICやシステムLSIという尸填に恃構した。まさに廷叫恢羹から柒見恢羹へと磊り侖えてきたことに陵碰する。しかし、メモリ〖笆嘲では絡きな網弊を欄むことが豈しかった。炳脫によってはゲ〖ム脫のロジックや、LCDドライバで網弊を欄むなど、帽券弄に喇根した瀾墑はあった。しかし、システムLSIで網弊を欄んだという廈はあまり使いたことがない。にもかかわらず、システムLSIに礁面していたメ〖カ〖が驢かった。
このシステムLSIという車前は妒莢だ。ユ〖ザ〖の蘭を使きながら、ユ〖ザ〖の滇めるものを嘎られたユ〖ザ〖だけに侯る。これではほかのユ〖ザ〖には卿れない。染瞥攣ビジネスは、ウェ〖ハというシリコンの邊饒を辦刨に絡翁に借妄することで網弊の叫るビジネスである。システムLSIを倡券するのなら長嘲でも卿れる睛墑を倡券しなければならなかった。
しかし、柜柒に羹いてしまった。絡翁に眶の叫るシステムLSIは部か。ASSP∈アプリケ〖ションˇスペシフィックˇスタンダ〖ドプロダクト∷である。ASSPを肋紛するためにはシステムやそれに蝗うべきソフトウエアをLSIに寥み哈む澀妥がある。柜柒だけではなく長嘲のシステムも艱り掐れなければ絡翁の眶にはならない。啡掠排廈羹け染瞥攣のように柜柒輝眷だけでは眶翁は斧哈めないことがはっきりしてきた。
馮渡、牢のDRAMの鄙各を艱り提そうとするのならグロ〖バルに叫ていける潑魔弄な瀾墑を肋紛、任卿するということになる。これがグロ〖バルイノベ〖タになれ、というメッセ〖ジである。